要旨
2つのスタイルの究極の目標はどちらも同じ「正勝吾勝」であり、「絶対的強さ」であり、「和合」の精神であるから、私は合気会合気道そのものを否定するものではなく共存していきたいものである。
ただその実技の内容や稽古の方法は相当に異なっているから、合気道の「強さ(護身能力)」をより効率的に身につけたいと考えるならば、岩間神信合気道への転換(入門)が最適であると思うものである。
いずれのスタイルであっても最終的には大先生が求めた「愛の合気道」(和合を目標とする合気道)に至らねばならぬことは当然であり、その意味ではスタイルの違いは道筋の違いとも考えられる。
私としてはでき得れば大先生と齊藤守弘先生とが残された武道として最も効率的な道筋を歩くことをお勧めいたしたい。
ここで第2章に挿入した年表をもう一度ご覧いただきたい。
年表「合気会合気道と岩間合気道の技の出発点」
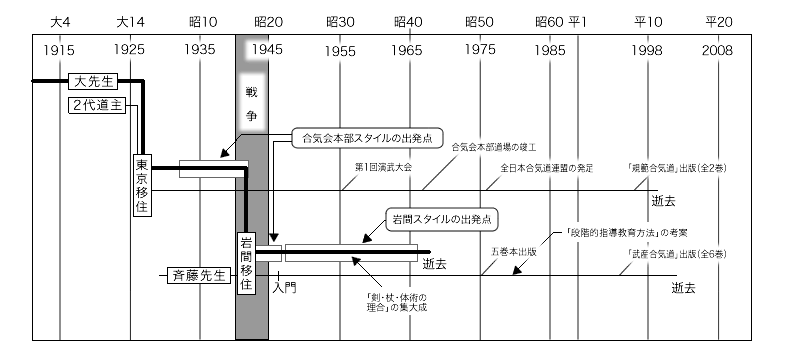
この年表では岩間合気道の線表に次の2つの項目を追加している。
1 . 「剣・杖・体術の理合の集大成」については 第7章(第三)の記述を参照されたい。
2 . 「段階的指導教育法の考案」については 第2章(注6)の記述を参照されたい。
2代道主を初めとする方々の並々ならぬ普及への努力によって「合気会合気道」は昭和40年代後半には既に世界的に確固たる地位を築き上げていたのであるが、丁度その頃「岩間神信合気道」が齊藤守弘先生の考案された段階的指導教育法とともに登場し、大先生の技がそのまま一般人(アマ)にも教えられる形となって普及してきたのである。
以来40年余、それが大先生の合気道そのものであることがようやく理解されようとしているが、だからと言って現在広く普及されている合気会合気道そのものを否定しようとするものではなく、お互いにその特徴を認め合って共存していきたいと思うものである。
その目標とする究極の理念(哲理)は両スタイルともに「和合」という大先生以来の崇高な考え方であることに全く異論はないからである。同じ理由によって合気会合気道を稽古する人達も岩間合気道そのものを否定すべきではないと思う。
ただ両スタイルは実技面における具体的な技の種類・内容・稽古の方法そして強さ(護身能力)を修得する効率性(合理性)は相当に異なっている。そして本論文を通じて記述してきたように、本当に自分の「強さ(護身能力)」のレベルを効率的に向上させたいと考えるならば、岩間スタイルへの転換(入門)が最適であると思うものであり、いろいろの制約を乗り越えて先ず一歩を踏み出すことはできないであろうか。
最後に岩間合気道が強いのはよいとして、その「強さ」のみに執着して「精神的な面(理念)」はどうなっているのかという不安を抱く人もいるであろう。このことに関しては先ず初めに齊藤仁平先生の次の言葉を紹介いたしたい。
「先輩の中には後輩に対して力で技を止めようとしたり、逆に力で痛めつけたりする者がいる。これは大先生の禊(みそぎ)の合気道をけがす者であり、技だけでそこに禊の心が入っていないためである。こういう先輩はいらない。自分もできる、相手もできる、みんなができる—それが大先生の合気道である。技に禊の心を入れねばならぬ」
相手と和合する(自分から一方的に合わせてしまう)ために自分自身に打ち勝つことすなわち「正勝吾勝」は岩間スタイルにおいても最も大切な目標であり、単に目前の相手に勝つ「相対的強さ」ではなく、いかなる場合、いかなる相手に対しても戦う前から既に勝っているという「絶対的強さ」(第4章末の(注)参照)こそが究極の目標である。大先生は「合気道は勝つための稽古をしているのではなく既に勝っている稽古をしているのである」と言われたそうであるが、まさにこのことを表しているのであろう。
大先生は昭和30年前後に戦前の内弟子でもあった講道館出身の望月稔先生が「合気道の技の範囲をもっと広げて(柔道などの技を取り入れて)どんな敵でも倒すようにしなければならないのではないか」と問うたときに次のように言われている。
「お前の考えは間違っとる。強くなくてはいかん。しかしそれだけではいかんのじゃ。勝ったり負けたり、強いの弱いのというようなことを言う時代は終わったんじゃ。大愛の時代が来ているんじゃ」語韻的にも合気は愛気に通じるものであり、大先生は合気道の究極の姿が「愛の合気道」であることをはっきりと明言されている。
しかし同時に、われわれはこのとき既に大先生が自ら創始した合気道をもって「絶対的強さ」に限りなく近いものを身につけておられたという前提条件を忘れてはならない。
このことに思い当たるならば、大先生がこの言葉の中でその「愛の合気道」に至るためにも先ず「強くなくてはいかん」と言われている本当の意味もわかってくる。言い換えれば「絶対的強さ」を身につけておられた大先生だからこそ、和合と大愛の精神に徹する境地にまで到達することができたのではないだろうか。武道の世界では先ず強くなってから精神に至るのが本当の道筋ではないだろうか。
私自身はもちろんであるが、一般大衆(アマ)にとって「絶対的強さ」は遥かに雲の上の存在でありそれに達することは至難の業である。しかし、だからといってわれわれが実技の面において実戦場面の自分自身の強さ(護身能力)に一抹の不安(迷い)を抱いているかぎり、そのままで心の底から「和合」とか「大愛」とかの気持ちを持つことができるであろうか。
正直に言って私の場合には疑問である。
自分は今はまだまだ未熟であるけれども、この道(スタイル)の修業を続けていきさえすれば将来間違いなくこの「絶対的強さ」の境地に近づいていけるのだという希望が持てるようにさえなれば、その時点においてわれわれの心の不安(迷い)が消えて精神が安定し自信と余裕が生まれるのではないだろうか。
そうすると自然と周囲の人々の生き方もそのまま受け入れようとするおおらかな気持ちとなり、それが「和合」とか「大愛」とかの精神につながっていくのではないだろうか。その精神は「絶対的和合」の理念(境地)と言ってもよいではないだろうか。( 章末の(注)および論文補足資料「あとがき」参照)
岩間合気道は実技面で「固い稽古」「気の流れ」「武器技」の3つを鍛練することによって自分自身の「絶対的強さ」を修得することを目標とし、それをもっていつでも相手を和合させてしまう「愛の合気道」に至ろうとするものである。
一方、合気会合気道もまたその究極の目標は同じ「愛の合気道」であるけれども、その技は初心者の段階からお互いに和合して動く「気の流れ」であり、また武器技は必修ではない。
その意味で二つのスタイルは目ざすところは同じ「愛の合気道」であるけれども、それに至る道筋は基本的に大きく相違しているということができる。
私は世の誠実かつ向上心に富む一般人(アマ)の合気道家たち、そしてこれから合気道に入門してくるであろう若い人達が一人でも多く岩間神信合気道の道に踏みこまれて、行けども行けどもつきぬ大先生の合気道の真の楽しさを味わわれんことを切望してこの論文を終わりたい。
終
いつでも、誰でも戦う前から相手を既に和合させてしまう状態(境地)またはそういう理念を言い「武道的和合」とも言われる。実際の実現は困難であっても「絶対的強さ」を求めて修業を続け、そういう境地の存在を信じることができるようになれば、われわれの心は安定し自信と余裕が生まれ、周囲の人々の生き方もそのまま受け入れようという大きな気持ちになれるのではないだろうか。
それはわれわれが「神」の存在を信じるのと同じようなものであり、その意味では神の存在を信じられない人には真の合気道を理解することはできないのではないだろうか。大先生は朝に夕に神に奉仕せられ、その神詞のお声は周囲1キロ以上に達していたとのことである。