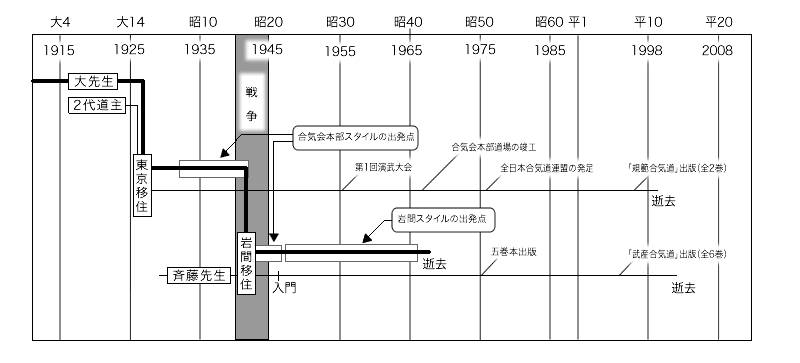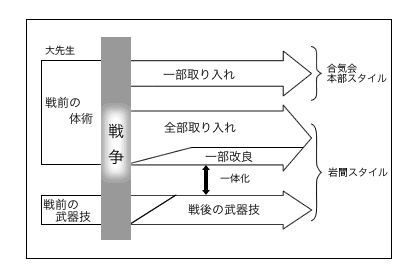要旨
大先生の合気道を基準に考えると、合気会合気道(合気会スタイル)は2代道主が戦後にその中の一部分(「気のながれ」の一部分 )を抜粋したものであり、一方、岩間神信合気道(岩間スタイル)は大先生晩年までの合気道そのものである。
従ってその歴史的経緯をみれば岩間神信合気道の方が20年以上新しい合気道であり、内容がはるかに豊富である。
先ず本論に入る前提として合気会合気道(合気会スタイル)と岩間神信合気道(岩間スタイル)の概要を表にしてみる。現在、組織に関係なく両方のスタイルが稽古されているが、人数の上では圧倒的に合気会スタイルの方が多い。
| 合気会合気道 | 岩間神信合気道 | |
|---|---|---|
| 中心 | 3代道主植芝守央先生—大先生の令孫 | ※岩間神信合気修練会会長齊藤仁平先生ー齊藤守弘先生の令息 |
| 時期 | 戦後、昭和20〜30年代に基本的な形が整った | 大先生の没後、昭和40〜50年代に基本的な形が整った |
| 概要 | 戦前・戦中・戦後(注1)までに大先生が教えられたものの中から2代道主(植芝吉祥丸先生)が体術の中の「気の流れ」の一部分を抜粋し一般に教えやすくしたもの(注3) | 戦前・戦中・戦後そして晩年(注2)に至るまでに大先生が教えられたものを齊藤守弘先生が一般に教えやすくしたもの(注3) |
| 特徴 | 体術のみ(注4) 体術は「気の流れ」のみで「固い稽古」なし(注7) 「気合い」なし |
体術および武器技(注5)および(注6) 体術は「固い稽古」から「気の流れ」に移る(注7) 「気合い」あり |
| 体術の数 | 約50種(基礎・基本の技)(注8) | 200種以上(基本技)(注8) |
| 目標 | 相手との和合を第一とする | 絶対的強さの上での和合を求める |
※齊藤仁平先生は平成15年11月、合気会から離れ「岩間神信合気修練会会長」として独立された。当初「岩間武産合気修練会」という名称を予定されたが合気会からの要望で改められた。
(注1)財団法人「合気会」の申請・認可は昭和23年2月であり、その頃までの大先生の技が合気会合気道の出発点となっている。その後、大先生は晩年まで茨城県岩間に居住され、時折東京の本部道場や関西方面への出張教授をされておられるから、その間2代道主が多少の改善はされたものと考えられる。
(注2)大先生ご昇天は昭和44年4月であり、その前年まで岩間で修業をされていたのであるから、戦後24年経過するまでの大先生の技のすべてが岩間合気道の出発点となっている。以後齊藤守弘先生は平成14年5月に逝去されるまで大先生の技の形そのままを保存し教授されてきた。
(注4)両方のスタイルの短刀取り、太刀取り、杖取りそして杖投げはいずれも体術の一部であって武器技ではない。
2代道主の著書には最後に組太刀、組杖、剣対杖をとりあげている場合もあるが、2代道主自身が「体術をしっかり身につけさえすれば武器技は特別な技法ではない」と言われておられるように武器技を体術の補助手段あるいは応用と位置づけられ、従って初心者には全く教えられない。
(注5)岩間合気道の「武器技」は剣、杖ともに「素振り」から始まる。剣の基本の素振りは7本、杖の基本の素振りは20本である。素振りができたあと合わせ、組太刀、組杖、剣対杖と続く一つの大きな体系となる。
武器技は初心者の段階から体術とともに教えられる。岩間スタイルでは武器技も体術も段階的に指導教育される。
(注6)「段階的指導教育法」とは、岩間合気道において初心者が入門してから5年、10年、20年と長く稽古を重ねていく過程で、大先生の合気道そのものを効率的に修得させるために指導者がとるべき段階的な指導教育法である。
その概要は次のとおりである。
岩間合気道の「体術」は「固い稽古」から始まるが、その段階では一つ一つの技を一つ一つの動作に分解して(必要なら番号をつけて)その正しい形と順序を指導する。それができたあとで相手に合わせる「気の流れ」へゆっくりから次第に速度を速めながら入っていき、自由技に至る。
「武器技」もまた先ず「素振り」から始まる。そのあと「合わせ」「組太刀」「組杖」「剣対杖」へと進んでいくが、先ず自分と相手が交互に動くように一つ一つの動作を分解して(間に2秒の静止時間をおく)鍛錬し、そのあと相手と合わせることを鍛錬し、さらに実戦的なものに入っていく。
この方法は昭和48年大先生のご逝去のあと、誰一人として武器技を継承し伝達できる指導者がいない中で、齊藤守弘先生が初期の岩間合気道の時代(「力の岩間スタイル」と呼ばれた )を乗り超えるために、実に10年以上の年月を費やして工夫考案・試行錯誤に心血を注がれ、昭和60年代に入って完成された画期的な指導教育法である。あくまでも「武器技」と「固い稽古」における基本的な形と順序を重視する稽古であると言ってよい。
これによって、現在一般人(アマ)でも大先生の合気道が稽古できるようになったのである。厳密に言えば大先生の合気道そのものは誰にも真似できないものではあるとしても、この段階的指導教育法によってそれに限りなく近づいていくことは誰にでもできるようになったということである。齊藤先生は晩年よく「技を途中で止められる人が合気道の上手な人」と言われていたものである。
私見を付け加えれば、段階的指導教育法は先ず武器技において導入され、次いで体術の固い稽古にも適用されるようになったのではないだろうかと思っている。
(注7)「固い稽古」とは「つかみ稽古」とも言われるように腕・胸・肩などを相手にしっかりつかませてから始める稽古のことである。あるいは相手にしっかりと打たせ、突かせ、あるいは蹴らせてから始める稽古のことである。
「固い稽古」の詳細については「第7章 岩間合気道の立場(第一)」を参照されたい。
これに対して「気の流れ」とは相手がつかもうとするとき相手の動きに合わせて動く稽古のことで、対照的に「柔らかい稽古」とも言われる。
さらに、合気会合気道の「気の流れ」は一種類であるが、岩間合気道の「気の流れ」はゆっくりやる場合(柔体技法)と速くやる場合(気体技法)とに分けられている。
(注8)合気会合気道の基礎・基本の技の数については植芝吉祥丸・植芝守央著「 規範合気道(基本編)」(芸術出版社、平成9年9月1日)および植芝守央著「 同 (応用編)」(平成13年6月10日)を参照し、岩間合気道の基本技の数については齊藤守弘著「 武産合気道(第1巻)」(合気ニュース社、平成6年8月31日)から「 同 (第5巻)」(平成13年3月1日)までを参照した。それぞれの著書は技の掲載・配列方法が異なっているが、比較対照しながらできる限り公平に数えるようにした。
この比較表の中で特に注意していただきたいことが2つある。
一つは大先生の晩年に至るまでの技(体術および武器技)が含まれているという意味で、合気会合気道よりも岩間合気道の方が20年以上新しい合気道であるということである。(上記(注1)・(注2)参照)
もう一つは一部抜粋と全部との違いであるから、岩間合気道の方が内容が豊富であるということである。
この二つの事情をさらに理解していただくために関係する部分の簡単な「年表」と「チャート」をつくってみると次のようになる。
この年表において
- 「東京移住」とは昭和2年(1927)の大先生および2代道主の京都府綾部から東京への移住、「岩間移住」とは昭和17年(1942)の大先生の東京から茨城県岩間への移住を示す。
- 「第1回演武大会」とは昭和30年東京の高島屋屋上において行われた公開演武会のことで初めて大先生が大衆の前で演武された。「五巻本出版」とは齊藤守弘著「合気道(剣・杖・体術の理合)第一巻〜第五巻(港リサーチ社、昭和48年9月1日〜昭和51年4月1日)」の出版を示す。
- 「規範合気道」出版(全2巻 )」とは植芝吉祥丸・植芝守央著「 規範合気道(基本編)」(芸術出版社、平成9年9月1日)および植芝守央著「 同 (応用編)」(平成13年6月10日)を示し、「武産合気道」出版(全6巻)」とは齊藤守弘著「 武産合気道(第1巻)」(合気ニュース社、平成6年8月31日)から「 同 (第5巻)」(平成13年3月1日)までを示す。
論文冒頭に紹介した前合気ニュース編集長スタンレー・プラニン氏の解説「武産合気道第1巻概説編」(平成6年8月31日)または「 同 新装版第一巻概説編」(平成22年3月10日)を読んでいただければ、この年表の概略は確認していただけるものと思う。
さらに植芝吉祥丸著・植芝守央改訂「合気道開祖植芝盛平伝」(出版芸術社、平成11年4月26日)および植芝吉祥丸著「合気道一路」(出版芸術社、平成7年10月20日)の最後のページには大先生および2代道主のそれぞれの年譜が詳しく載せられているので、この年表と照合されて確認していただければ幸いである。
このチャートは、2代道主が大先生がつくられた技の中から比較的わかりやすくて「気の流れ」に適した技を取り上げられて合気会合気道とされ、一方岩間合気道には大先生の晩年までのすべての技が含まれていることを示している。さらに大先生が戦前の武器技を改良されて体術と一体化した新しい武器技を集大成されたことを示している。
「武器技」の不可欠性などについては「第7章 岩間神信合気道の立場(第三)」を参照されたい。
以上の二つの事実(スタイルの新旧と技の種類の数)を総括してみると「合気会合気道は2代道主が戦後に大先生の技の中の気の流れの一部分を抜粋したスタイル」であり、「岩間合気道は戦後24年間かかって大先生が岩間で完成されたスタイル」であるという事実を改めてご理解していただけたら幸いである。
そうすると世間でよく言われる「合気会合気道は大先生晩年のなめらかな気の流れ中心の技であり、岩間合気道は大先生が若い頃やられた直線的な力の技である」というような評価が全く事実に反したものであることもご理解いただけるのではないだろうか。
戦後の合気道界の歴史的経緯そして大先生・2代道主および齊藤守弘先生の動静などについては第6章 に記述する。