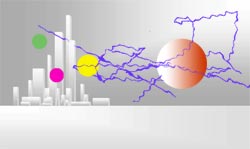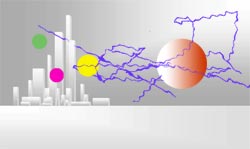ボリス・ヴィアンは何でも屋でした。技師、俳優、ジャズプレイヤー、歌手、画家、小説家、シナ
リオライターetc.彼の活躍した40〜50年代に、それらの職業を全てひとつにまとめた形のアーティストは存在しなかったかもしれないけれど、20世紀
のテクノロジーの進歩は、言葉も映像も音楽も自在に操る芸術家や、監督・脚本・主演をこなす役者のような、マルチアーティストの存在を可能にしました。
ヴィアンも、あらゆる表現の可能性を追及したマルチアーティストだったという意味で、極めて20世紀的な作家だと考えられます。しかし、ヴィアンは同時進
行で様々な活動をしたとは言え、彼は確かに小説という表現方法に当時最大限の可能性を託したのでしょうし、その作品は、生前はごく一部の人にしか理解され
なくとも、発表後半世紀を経た現在まで若者の関心をとらえ、しかも1作品に限らずヴィアンの多くの小説が版を重ねて出版され続けてきました。ここでは『北
京の秋』の中の3つのキーワードを軸に、ヴィアンの現代性を探り、「砂漠に鉄道を引く」とは
何かを考えてみます。
1.「見るべきもの」
小説は、アマディスが975番のバスに乗ろうと四苦八苦する場面から始まります。
満員だったり、番号札を取り損ねたり、バスにかわされたりして結局乗れず、アマディスはバスに乗れそ
うな停留所まで戻るのですが、その間にバスに乗る目的よりも「見ておくべきものが沢山あるように思え」て、
そのまま歩き続けてしまうのです。この「見るべきものはたくさんある」という言葉は、小説の
終盤、自殺を考えるアンジェルと神父プチジャンとの間でも交わされます。
「きっと、あなたのいうとおりかもしれない。あな
たは大した男ではないし、何も見ていない」とプチジャンがいった。
「砂が見えます」とアンジェルがいった。
「あの鉄道・・・バラスト・・・(略)
「いうことはできます。しかし、それをいうよりもほかの
何かです」とプチジャンがいった。
・・・(略)・・・
「考えさせて下さい。見るべきものはたくさんある」アン
ジェルがいった。
・・・・・
「見ようと思うものはなんでも見えます。それに見るとい
うのはいい。しかし、それでは充分ではない」とプチジャンがいった。(p375〜376)
では、「見るべきもの」とは何でしょうか・・?。
20世紀の幕開けの時、1900年のパリ万博で初公開された映画は、全く新しい視覚文化をもたらし人
々の「見る」意識を変えていったし、見る出版物としてのアニメーションの流行も20世紀の視覚文化の代表的なものといえます。映像やアニメーションという
新しい視覚芸術は、物の形状や、印象、さらには見えないものを見、過去に見たものを見る、という風に、形態的にも時間的にもそれまでの「見たまま」「在り
のまま」という概念をくつがえしました。ヴィアンの描写には特にアニメーションや劇画に通じる表現が多く見られます 〈注1)。
感情のままに色を変えるバスやタクシー、昨夜の顔を残したままの鏡、好き勝手に移動する太陽や方位、
足から根が生えて動けなくなる人間、等々。。。そして、言語を分解再構成し、読者の思い込みや想像を逆手に取って翻弄するかのようなヴィアン特有の「言葉遊び」もたくさんあるようで、それらも、文字を見た時に感じる視覚的効果、言葉を聞いた時に感じ
る聴覚的効果など、コミック文化やアニメ映画に通じる面白味をもたらしているように思えます。原書を読んでいないため詳しい論証はできませんが、『北京の
秋』に登場する人物の思わせぶりな名前に関しては、ヴィアンの変名であるヴァーノン・サリバンと、
ヴィアンが好きなJAZZミュージシャン、デューク・エリントンを重ねた、<ヴァーノン・デュークによる歌>なんていうのが出てきたり、アルフレッド・ジャリを思わせるアルフレッド・ジャーベな
んて名前が使われています。このような「言葉遊び」に加えて、先にあげたようなアニメ的なドタバタ劇風の表現の斬新さが、映像や音楽に馴染んだ現代の若者
に受け入れられる要因なのでしょう。
1946年という年は、ヴィアンの執筆活動が猛スピートで動き出した年で、『うたかたの日々』
がガリマール社主宰の文学賞候補となり、最終候補で落選。秋にはこの『北京の秋』が執筆されます。ヴィアンはサ
ルトルの主催する『レ・タン・モデルヌ』にも寄稿を始め、『うたかたの日々』
では、一部をまず同誌に掲載したそうです。しかしヴィアンは、「私は実存主義者ではない。事実、実存主義者
であれば実存は本質に先立つ。私にはその本質がないのだ」(アルノー、P244)という発言にもあるように、サルトルの実存主義とは一線を
引き、あらゆる主義、運動から自由であろうとしました。サルトルに対しては、ジャン・ソル・パルトルと
いう名で『うたかたの日々』の中でもカリカチュアして描き、パルトルは終いには、パルトル信奉者の恋人から「心臓抜き」という器械で殺されることになりま
す。
ヴィアンは、サルトルの作品『嘔吐』についても、パルトルの著作『嘔吐百科』として登場させていますが、一方で『サルト
ルと糞』(アルノー、P243)などというエッセイ(これも誉めているのか嘲笑なのかわからないようなものですが)を『街路』誌に発表し、
その中ではサルトルを擁護している姿勢を一応はとっているようですが、サルトルが次第に強めていく政治的姿勢、「アンガージュマン(社会参加)文学」に対
しては批判的だったのでは・・?と見られています。
「現実参加(アンガージュマン)が、問題になりま
す。ジャン・ソル・パルトルの理論に従った現実参加(アンガージュマン)・・・・。植民地の軍隊に参加(アンガージュマン)、あるいは再加入すること。そ
れに、個人が召使を月給で参加(アンガージュマン)させること、あるいは、雇い入れること、その三つの間に何か並行的な関係があると、我々は見てるんで
す」(『うたかたの日々』P34)
『うたかたの日々』の中でサルトルの論をこんな風に揶揄してみたり、「政治的解決法など何にもならないのだ。また政治的分析がいくら秀れていても結局はやはり何もならない」(『アンダン
の騒乱』解説より)というヴィアン自身の発言があったり。。
ヴィアンはまた、固定的な視点で判断を下すことを嫌いました。「ボリス・ヴィアンは一般に文学論争に対して好感を持っていなかった。彼は<批評>や<分析>(彼の用語によれば)を
生涯呪い続けた」(アルノー、P241)とあります。
以上のようなヴィアンの姿勢から推測してみれば、『北京の秋』の砂漠というのは、自由に形を変える砂
丘、何もかものみこむ砂、そして、あらゆるものをあまねく照らし出す太陽という象徴からも想像できるように、ヴィアンの求める表現の可能性を示す場である
と思われるのです。
『北京の秋』の特徴的な構成として、章のところどころに挟まれる「パッサージュ」という「つなぎ」の部分があります。「パッサージュ」では作者自身が顔を出し、物語の
解説をし、今後の方向づけを語るのですが、その最初の「パッサージュ」にはこんな風に書かれています。
「砂漠は広広としている。故に、人はそこに集まり
たがるものである。彼らは、ほかのいろいろなところでやっていたことを、そこでふたたびやりなおそうとする。砂漠でだと、そんなこともまた、目新しく見え
るからである。砂漠は、何物をも鮮明に見せる背景となす」(P65〜86)
「見る」とは、それまでの表現活
動では試みられなかった事物のとらえ方、その表し方のことであり、その「見るべきもの」が「たくさんある」とは、表現の自由さ、可能性の広さを示している
のではないかと思うのです。
・・砂漠という無限の場所で、何もかも今までになく新鮮に見つめ、それらを自由に表現する・・そのよ
うな、想像力による可能性・・そう、ヴィアンのパタフィジックの精神です。「見える」ことへの懐疑、「見るべきもの」は何なのか、そして「見た後」はいか
にすべきなのか、「見ること」への考察は奇抜なストーリーの内部で最後までつづいていきます。